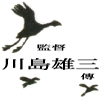 |
99/06/11 監督 川島雄三傳 『幕末太陽傳』 |

| 壱 | 八ツ山〜品川宿入口 | 五 | 海蔵寺(投込寺) | |
| 弍 | 土蔵相模跡 | 六 | 千躰荒神海雲寺 | |
| 参 | 品川宿お休み処 | 七 | 英国公使館跡 | |
| 四 | 品川橋 |
| ■ オープニング・タイトル検証 〜 八ツ山あたり [地図壱] 毎日通勤で通過している品川駅から、めったに乗らない京浜急行の下り各駅停車で一駅、旧品川宿の入口である「京急北品川」という駅に降り立った。その間わずか500m、時間にすると1分半ほどである。「もしかしたら、歩いても良かったかな」と思いながら、『幕末』の冒頭を飾る八ツ山付近を撮影しようと、品川駅側に戻っているうちに...本当に品川駅に辿り着いてしまった(笑)。 少々ズッコケつつ、持参したビデオからのプリント・アウトと周囲の風景を比較する。まずは印象的な八ツ山陸橋の遠景。「製作、脚本」などのスタッフロールと重なっているあの構図である。手前を第一京浜国道が走り、陸橋を越え上方から品川宿に入って行くというアングルは、かなりの高度から撮影した俯瞰である。その場に立って見渡すと、第一京浜沿いの三菱地所の施設「関東閣」からのものと判明。しかし私は三菱の社員ではないので侵入は諦め、道路沿いのガードレールに乗って(通りがかりのヤングギャルから"京急狙いの鉄道マニヤ"に間違えられながら)写真を撮る。 陸橋にはまさに京浜急行の快速特急がさしかからんとし、その後方にそびえ立つのは今年('99年)初頭に開業したばかりのオフィスビル群「品川インターシティー」である。タイトルに登場した昭和32年のその場所は、倉庫や工場が密集し、すぐ後ろが入り江になっていた。40年程の間に埋め立てが進み、開発の中心となっている三菱グループは丸の内の"三菱村"からこの地への一大移転を進行させている。数年後には新幹線の品川駅も開業予定であり、都内でもちょっとホットな場所といえる。 宿場街としての栄華を誇ったのが今から百数十年前のこと。維新後は一時さびれたが、最近の東京湾岸開発の波に乗り(微妙に位置は違うが)品川の街は再び盛り上がりを見せてもいるのだ。 (陸橋の様子が大分変わっているが、これは昭和60年に架け替えられたためである。映画に登場するのは昭和5年竣工の3代目、現在のものは4代目となる。ちなみにこの地点、正月の「大学対抗箱根駅伝」で御存知の方も多いだろう) |
 |
 |
八ツ山陸橋 昭和32年 平成11年
| さてこの一帯、御殿山周辺は今も昔も超高級住宅地であるようだ。そもそも御殿山とはその昔、徳川家康が館を設けたところから付いた名前で、明治維新後も財閥系富豪達のお屋敷街となっていた。そして今は「御殿山ヒルズ」などの"億ション"が林立している。 十数年前にこの地に出来た「ペアシティ・ルネッサンス」が、今考えてみれば"元祖・億ション"のようなもの。最上階には冨田勲氏の自宅兼シンセサイザー・スタジオがあり、三浦友和・百恵夫妻もここに住んでいた。 地図と風景を比べているうちに、八ツ山から線路沿いに大井町側に行った「権現山公園」が、高杉晋作たちが焼き討ちをした「英国領事館」跡地であることがわかる。むむ、それこそ毎日会社の行き帰りに眺めているぞ。灯台下暗しの極致である。 |
 |
 |
品川宿入口 昭和32年 平成11年
右の写真、左側から京急の列車
| 『幕末』のキャメラは陸橋を渡る自動車を追い、右手にパンする。低いビルの横でキャメラは通りを捉え、ここが「品川宿入口」として紹介される。ビルこそ高くなったものの、ここは今でも当時の面影を残している。今回ヴィデオをじっくり観て気付いたのだが、この通りが映るシーンで、キャメラの移動に合わせて踏切の遮断機が降りている。これは陸橋から続く京浜急行の踏切で、写真でご覧の通り、今でも全く同じ構図を収める事が出来る(ちなみに今度はぐにゃぐにゃの自転車に乗ったホームレスから"道に迷っている子供"と間違えられる。親切はアリガタイが、30男に向かって「お坊ちゃん!!」はネェだろうがヨ)。 ちなみにこのシーンを走り抜ける白い屋根のスポーツカーはスケジュールが合わず出演出来なかった川島組常連、三橋達也氏のものらしい。 |
| ■ いよいよ品川宿へ 〜 相模屋のいま [地図弍] さてこの踏み切りを渡り、旧東海道品川宿−今の呼び方は「北品川本通り」−を歩いてみる。「相模屋」発見にわくわくするが、それはあまりにもあっけなく見つかった。踏切から3分程の「ファミリーマート北品川店」(北品川1-23)が相模屋の跡である。 そんなかけ離れたものになっているにもかかわらず、なぜすぐ判るか...地元では「あの店が相模屋のあと」として有名なのである。品川宿を説明した冊子やホームページに、「相模屋跡」として必ず出ている。ちなみに相模屋は明治維新後も宿屋としての営業を続け、実に戦前まで映画のままのあの建物だったそうだ。その後改築をして、タイトル部分に出てくる「さがみホテル」の建物になるが...惜しい!タイトルに登場した建物が、今のコンビニに変わったのは僅か10年前のことだという。10年マエ、私ハスデニ川島ニハマッテイマシタ!無念、もっと早く訪ねるべきであった。 |
 |
 |
昭和32年の「さがみホテル」とその跡地、平成11年のファミリーマート北品川店
右の写真、手前の男性は奥の女性をつけている訳ではナイ、と思う
| ここで気になるのが、劇中に度々登場する「相模屋の桟橋」だ。おそめと金造が「品川心中」を企て、高杉と若旦那たちを佐平次が逃がした、あの桟橋である。先程書いた通り、相模屋は海岸線に沿った斜面に建っており、通りから見ると2階建て、海側から見ると3階建ての様に見えるそうだ。その海側、地階の際から桟橋が出ており、いくつかのドラマがここで起こる。しかし、ということはここまで海が迫っていたのか...。 ファミリーマートの先から路地を左に折れてみると、なるほど数十メートルほど急な坂道で降下している。その先は...なんと、すぐに入り江であった。天王洲から続く運河の先端(品川浦)で、本通りに並走するここ「八ツ山通り」がかつての海岸線であったそうだ。本当に相模屋のすぐ裏は海だったのだ(但し桟橋の有無については議論を呼んでいる模様)。 |
| ■ 地元で聴く、品川遊廓のその後 〜 品川宿お休み処 [地図参] 本通りに戻りしばらく歩くと、右手に「東海道品川宿・お休み処」という真新しい建物がある。「旧東海道品川宿周辺・まちづくり協議会」という地元の団体が運営する無料の休憩所だ。事前の調査によるとここで「まち歩きマップ」なるものが貰えるらしい。 迷わずお邪魔すると...とんでもないものを発見してしまった。「まち歩きマップ」に並べて、三栄書房の雑誌『ラパン』創刊号('95年11月発行)があり、表紙には「小沢昭一の品川三昧」とある。「小沢昭一?『幕末』の貸本屋金造役じゃないか。もしかして...」と開いて見ると、やはり映画『幕末太陽傳』を中心とした品川宿探訪であった。ストーリー紹介、撮影裏話、品川遊廓の変遷など...貴重な資料として嬉しいような、先を越されて悔しいような複雑な気持ちになる。しかしそこはそれ、一般誌ゆえ、斬り方は"それなり"。「よし、川島ファンならではの、バサっとした斬り方で攻めちゃる!」と決心する。 |
| お休み処はなぜか、非常に和気あいあいとした雰囲気で、初対面の人達同志が品川の思い出などを語っていた。「赤線がぁ、廃止になったのがぁ...」と考え込んでいる年配の男性に「昭和33年の4月です」と助け船を出したことから、私も話の輪に加わり、貴重なお話を伺うことが出来た。 まず、謎だった「赤線廃止後の変遷」。昭和33年の閉鎖後、「特飲街」の店々はお好み焼き屋、焼鳥屋などの飲み屋と下宿屋になったという。小振りの厨房を使い簡易な飲食店に、貸し座敷を活かし下宿屋に、というわけだろう。 下宿屋には大崎の立正大学、品川の東京水産大学の学生が多く住んでいたが、下宿屋のお姐ィさんの中には元"そういうご職業"に就いていた方などもいらっしゃって、明日を担う学生諸君に非常に実践的に「人の道」などを説かれていたそうだ。アリガタイコトデス。 |
 東海道品川宿・お休み処 |
| たまたま同席したその男性は、この地にかなりお詳しいらしく、「チョンの間500円」なる貴重なお話も伺えたが、女性読者もいるのでこのへんで切り上げてよう。ちなみに「赤線時代からここにいる」という老婦人は、息子さんが幼いころに「なんで夕方になると綺麗なお姐ィさんがいっぱい歩いているの?あの人たちはなにをやっているの?」と問い詰められて、返答に窮したそうな。 |
| ■ こはるの墓サ案内すっダ! 〜 品川橋から投込寺・海蔵寺 [地図四、五] お休み処を後にし、旧東海道を歩く。実はしばらくは単なる「地味な商店街」である。映画の中では荒神様の日はかなり離れた相模屋付近まで提灯飾りが並び、往来も激しいようだったが、残念ながら今はそうではなかった。 10分程歩くと「目黒川」にかかる大きな橋に辿り着く。むむ、ここは覚えがあるぞ。ここもオープニングで出て来た。「品川橋」と「品川橋通りアーチ」の場所だ。橋は横に大きく拡張され、庭園風の植え込みや、小さな庵なども作られている。デザインは変わったがアーチは健在。そして橋の上から河口に目をやると...先日開業したばかりの、お台場"パレット・タウン"の大観覧車が見えた。 なるほど、そういう位置関係であったか。古い宿場町と最新のトレンディー・スポットがこのように接近しているというのも面白い。ちなみに川の上流には「品川図書館」、助監督・今村昌平、浦山桐郎が川島に命ぜられて、この地の歴史を調査した場所である。 |
 |
 |
品川橋 昭和32年 平成11年
| さらにここで、ふと思い立つ。映画のラストに出てくる、佐平次が千葉の田舎親父・杢兵衛(市村俊幸)を振り切って逃げ出す、あの寺がこのあたりの筈だ。「ここまで来たら...」と、そこも探してみることにした。 シナリオによれば寺の名前は「海蔵寺」(南品川4-4-2)。相模屋と荒神様の中間にあり少々内陸側に入る。現在は住宅街のど真ん中になっており、「なんでこんな処を重要なラストに持って来たのか」と不思議に思いながら訪ねると、意外な発見があった。 |
| この海蔵寺、またの名を「投込寺」(なげこみでら)と言い、品川宿の"裏面"を担って来た処だという。品川区の指定史跡にもなっているここの「無縁塔群」はかつてこの地にあった溜牢(ためろう−牢屋のこと)で亡くなった人々の遺骨を集めて作られた塚で、その後、天保の大飢饉の死者や、鈴ヶ森刑場で処刑された者の首(鈴ヶ森送りの罪人の姿は姿は映画にも一瞬出てくる)、そして品川遊廓の娼妓の大位牌も祭られているそうだ。 生きている芸者を死んだことにして、煙に捲くというこのくだりは落語『お見立て』の引用であるが、なるほど仮にこはるが埋葬されるならば、この「投込寺」が適当なわけだ。 |
 海蔵寺 ここから佐平次が逃げ出した |
| 再び旧東海道に戻ろう。実はこの品川橋付近でひと駅分歩いている。目黒川の上に掛かる高架駅が北品川の次、「京急新馬場駅」である。ここから荒神様のある京急青物横町駅付近まで、さらにひと駅分歩くわけだが...こここそ徹底的に地味な商店街であった。しかも日曜休業の店が多い。但し距離は短く、10分かからずに青物横町駅から続く「ジュネーヴ平和通り」(すごい名前だがジュネーヴと品川は姉妹都市なのだ。品川寺にはジュネーヴ帰りの鐘なるものもある)と交差する。 ここまで来るといよいよ縁日が並び始める。人通りも多く、お祭りの感じがやっと出て来た。100mほどの縁日を抜けると右手に本日の最終目標、「千躰荒神・海雲寺」(南品川3-5-21)が現れる。 |
| ■ 映画の謎、いろいろ判明す 〜 千躰荒神海雲寺 [地図六] さて、私は昭和32年の「川島組」と同じ処に辿り着いた。海雲寺護摩堂(本堂)である。ヴィデオからのプリントを片手に眺めると、右手に「〜如車輪」と書いた柱があり、奥の上方に「王神荒」の扁額(文字額)、全く同じ構図である。荒神様に吸い込まれて行く人々のショットが、セットではなくまさにここで撮影されたことが判る。 ここはひとつ、同じアングルで写真を撮りたいところだが...ここで私は「川島的構図」を身をもって知ることとなる。右手の柱の文字と、本堂上部の扁額を映画と同じ角度で入れようとすると、ほとんど地面に接するが如く身を落とし、更にかなり斜めに構えなければならないのだ。人間の目線を超えた、川島特有の「カメラの見た目」は有名だが、なるほどこんな僅か数秒のショットにも、ユニークなセッティングが隠されていたのか。 神社・仏閣を撮るときに良く見られる構図ではあるが、それにしても、妙にナナメなのだ。荷物を置きしゃがみこんで(非常に妙な姿勢で)、どうにか一枚撮ってみる。 |
 |
 |
海雲寺護摩堂入口 幕末と現在
| 本堂に入る。この荒神様は火と水の神、また台所の神として有名である。劇中で山岡久乃演ずる相模屋の女将が「火を粗末にするんじゃないよ。荒神様のバチが当たるよ」と言っているのはそのためだ。江戸期に起こった何回かの大火が、この海雲寺付近まで来るとなぜか鎮火した、というのがその由来だが、地元の人々の「火伏せの神様」としての信仰は今でも篤く、私が住んでいるマンションの入口にも荒神様の御札が貼ってあるくらいだ。 このお祭りのシーンで一瞬ではあるが、火をくべる僧が映る。この業、「護摩修行」は今でも行われていた。本堂の中心に「御護摩どころ」と書かれた仕切りがあり、そこで同じ光景を見ることが出来た。これはまず、入口で「ゴマ木」という白木の棒を金二百円也で購入。そこに名前と年齢を書きお坊さんに渡す。するとそれを火にくべて、お祈りをしてくれる、というものだ。3月、11月の大祭の他に毎月1日、15日、28日の「護摩日」にも時間を決めて行われているそうだ。 私も「心願成就」のゴマ木を買い、お祈りをして貰った。フラッシュを焚かず、映画と同じアングルで写真を撮らせてもらう。 |
 |
 |
護摩修行 幕末と現在
| さて、ひとつ気になることがある。貸本屋金造との「品川心中」騒ぎで風邪をひき寝込んでいるおそめに、遣り手婆ァのおくま(菅井きん)が買って帰った「これはわたしのお見舞い」だ(上の護摩堂入口左側の写真でも持たれている)。笹の先に紙の飾りが付いており、荒神様帰りの人は皆提灯の様に手にしている。今でもお土産として売っているのかと思ったが、残念ながら見つけられず。その「正体」もわからないので、休憩所にいた法被(はっぴ)を来たご老人たちにプリント・アウトを見せて尋ねてみた。 するとその中のひとりが「あぁ、これは『やぁとこせぇ』だ」と教えてくれた。単なるおもちゃで意味は判らないとのこと。今は売っても、作ってもいないそうだが、昔のものが寺務所にあるかもしれない。「ちょいと来なよ」とすぐ案内してくれる。バカにハナシが早ェえのがさすが、江戸っ子(笑)。「なんだなんだ?」と周囲の人達数名も付いて来る。ちょっとした騒ぎになってしまった。 「やぁとこせぇ」は残念ながらなかった。なくなってしまったわけではなく、寄り合い部屋に飾ってあったのだが、なにしろ古いものなので仕舞い込んだらしい。現物は見られなかったが、その「正体」が判りまず満足。でも映画同様、片手に握って家まで帰る事が出来たら、もう、最高だったのだが...。 さてこの「やぁとこせぇ」、ここでは意味不明だったが後日、書籍『品川の民俗と文化』(昭和45年・品川区刊)により詳細判明。となり町、大森の郷土玩具で、「住吉踊り」と呼ばれることもあるようだ。笹竹の先に大きな輪が下がり、その輪にさらに数体の小さな人形が下がっている。これを手に持って揺らすと、その動きが伝承舞踊の「住吉踊り」に見えるようになっているのだ。材料は麦藁で、一種の藁細工である。 なんとも楽しい玩具だが、見られなくなってしまった理由は「大森で藁が採れなくなってしまったから」だった。残念ながら東京都大田区に麦畑はもうない。 かわりにもうひとつの名物、「釜おこし」を買って帰った。その名の通り、お釜の形をしたおこしでこれも歴史のある名物品である。「お釜の底叩くんじゃないよ!荒神様のバチが当たるよ!」再び山岡久乃の台詞が聴こえて来そうだ。 屋台のおばさんに「写真を撮らせて下さい」とお願いすると、カメラ目線で笑顔まで見せてくれた。ラストは元気そうなおばさんの写真で。まさか自分の姿がインターネットに載っているとは思っていないだろうなぁ(笑)。購入した釜おこしはアップの写真を撮る前にむしゃむしゃと食べてしまった。御免!。 |
 |
 |
釜おこしのおばさんと旧東海道の賑わい
| なおこの界隈が本当に賑わうのは6月初旬に行われる品川神社「北の天王祭」の様だ。なかでも土曜日の夜8時ごろに行われる「おいらん道中」の時には旧東海道に身動きが出来ない程の人が押し寄せるらしい。要再取材(平成30年追記:現在は北の天王祭は6月初旬、おいらん道中は9月最終週に行われています。元々近所でしたがこの記事のあと相模屋のすぐそばに引っ越し「天王祭の『品川拍子』で篠笛を吹け」と誘われています…)。 |
| ■ 取材を終えて 〜 語られていなかった「川島の設計」 川島は昭和37年の作品『青べか物語』の製作時、主役の森繁久弥にたった一言、舞台となった浦安の海岸が「やがて埋め立てられる」と語らせるために助監督(東京映画の山本邦彦氏)に埋め立て計画の全貌から、施工方法の細部まで徹底的に調べさせたという。また昭和34年の『貸間あり』では主人公たちに劇中でロールキャベツを作らせるために、シナリオの共同製作をしている藤本義一氏をロールキャベツ職人である旧友の元へ送り込んだ。 川島雄三という人間は、その世界のことを熟知していなければよい脚本(ホン)は書けず、よい絵も撮れない、と思っていたようだ。映画製作のため、ある程度の事前調査は当然のことであるが、どうも川島のそれは徹底的、いや偏執的とまでいえるものがあった。 川島を巡る様々な記録を読むと、どうやら「博覧強記」たるものへの異常なまでの憧憬があったようなのだ。シナリオの創作現場には何冊もの辞書が置かれ、突然、思い出した様に「これはドイツ語ではなんというのか」とか「フランス語では」と共同製作をしていた助監督たちに問うていたそうだ(ちなみに「××です」と正確に答えていたのが東大出の秀才、中平康。藤本義一氏は適当に答えていたらしい)。 フランス文学から江戸文化まで、一種博物学者的な執着を持っていた川島の才能が非常に的確な形で映像化されたのがこの『幕末太陽傳』なのではないかと思う。とにかく今回、佐平次を追って品川宿を歩き廻り、痛感したのはそのディテールの鋭さであった。 死の2本前となる『喜劇とんかつ一代』(昭和38年)ではその「調査結果」が台詞となって並べられ、少々あざとくも感じられた。しかしこの『幕末』では、物語と、台詞と、風景の中に消化(昇華)され、見事に骨太な、かつ密度の濃いの作品となっているのだ。 ともかく驚くべきは徹底的な幕末・品川宿の再現である。まず舞台となった「土蔵相模」については前述の通り。また、街並みまでも比較してみると、写真の通り相模屋付近の旧東海道の一部をかなりのスケールで再現していることも判った。 この『幕末』製作にあたり日活と費用面で激しくモメたのは前述した。しかし川島は「セットをもっと丈夫に。費用などいくらかけても構わない」と言い続けていたそうだ。 |
 |
 |
東海道新馬場側から八ツ山方向
幕末のセットと現在の同地点 右奥が相模屋
| もちろんこうしたセットの問題だけではない。当時の「食売旅籠」の風習に対するこだわりも凄い。何気なくインサートされる下足札を玄関に叩いて散らす開店時の段取りから、設定、台詞に至るまで、全くの無駄も矛盾もない。品川宿そばの出身で、赤線時代も良く知る登場人物のひとり、小沢昭一氏は、最近のインタビューで「この映画は動く文化財、歴史博物館といってもいいくらいだ」と語っていた。 「荒神様」の祭事や土産物までも忠実に再現されているということも判った。さらには現地の人間でなければ判らないような微妙な舞台設定−投込寺・海蔵寺など−もあった(このあたりが今回の取材の最大の収穫でもある)。 もう一歩、踏み込んで考えてみよう。なぜゆえにここまで幕末の庶民文化に−まるで取り憑かれた様に−執着したのだろうか。川島の言動を追って行くと、権威的なものに反抗し、庶民的なものにこだわる感覚が強く見受けられる。そうした庶民のエネルギイ、前出の川島の言葉で言えば「ヴァイタル・フォース」を映画の、映像のパワアにしようと試みていたようなのだ。 これはこの作品に限ったことではない。そして結果これは映像的には一種の「戯作趣味」として顕れていた様に思う。川島映画の最も象徴的な部分であり、その洒脱、粋の根源ではあるが、同時に彼が「風俗作家」などと云われてしまう(片付けられてしまう?)所以でもある。 しかし当然、これは無価値に軽佻な風俗描写ではない。その本質として、江戸期の式亭三馬や十返舎一九、更には井原西鶴から織田作之助へと連なる戯作、町人文学の系譜上に映画という極めて近代的、工業的な手段を用いつつ自らが位置したかったという強い思いがあったのではないだろうか。 織田作之助−川島の監督デビュー作の原作者にしてシナリオも執筆、その後も篤い親交を続けるも志半ばにして病に散った重要な作家である。その織田作の遺志を継ぐべく全力を尽くした川島ではあるが、やはり病に倒れ夭折してしまったというのは返す返す残念に思える(そしてその系譜上に居るのが、若き時、川島に師事した藤本義一氏のようにも思うのだが...)。 ディテール表現に戻ろう。天皇・黒澤明監督の「完全主義」は有名である。画面に映らない小道具をどうしたとか、登場する書類の文面をこうしたとか、さも貴重なことの様に語られているが、ここまで繰り返し検証して来た通り、川島とて同じことをやっているではないか。 しかも史実を詳細に調べなければ判らないような意味的、象徴的な部分にまでもこだわっている。変な話だが、ラストに登場する寺などはわざわざ海蔵寺にせず<海沿いの寺>という設定だけでも十分なのに、である。また詳しくは書かなかったが、一瞬しか登場しない「起請文」や人置の「証文」(大工長兵衛(植村謙二郎)が娘おひさ(芦川いづみ)を相模屋に売ってしまう時に登場する。長兵衛は字が読めず、拇印を押す場所がわからないという演出があった)の全文がシナリオには記されているのだ。 そしてこうした「黒澤−川島比較」の要となるのが、黒澤が芸術としての完成度を求めるために細部に執着したことに対し、川島は「粋の再現」、更には前述の通り、自らもその世界の中に身を置かんとするために執着したということである。 また時代劇を侍の側から描いたのが黒澤、あくまで町人の側から描いたのが川島という対比も可能だ。 正直ここが川島評の分かれ目でもある。高尚な黒澤芸術に対し、風俗作家・川島などと片付けられてしまう原因でもあることは先程も書いた。しかしここまで繰り返し検証した通り、製作にかける労力と深さについては黒澤に引けをとらない。むしろある部分に於いては黒澤よりも「深い」と思わせるところすらある様に思うのだが...。 黒澤映画には黒澤なりの魅力があり、もちろん私もよく観るし、ファンであるともいえるのだが、黒澤研究本に何回も登場する『赤ひげ』の薬棚の逸話などを見ると、正直「またか」と思う様なところもある。さらにそれを周囲が異常なほど持ち上げて書いており、その感覚にはハッキリ言って違和感がある。どうも「崇拝」「賛美」という感じが苦手なのだ。「崇拝」「賛美」の文体は時として客観的な評価から外れることがある。 むろん私はここで「川島崇拝」を記そうとしているわけではない。只、数々の「伝説」の残されている黒澤や、キャメラや光線など撮影技術の分析が盛んな小津、構図設計についての研究本が出ている溝口、成瀬らに比べ、川島のこうした緻密な「設計」についてはあまりにも語られていないのではないだろうか。いや−ここで書いた様な実地検証を伴った−分析がなされているのか否かすら怪しい(空間分析についてのみ唯一'89年に記された加藤幹郎氏の名文がある)。 以上、映画好きのいちサラリーマンが、週末の休みを使って調べた稚拙な雑文ではあるが、川島作品の舞台設定や構図についてさらなる研究のきっかけになれば幸いである。大学映研、映画学校の学生など、あとは頼んだ!。 |
 |
監督・川島雄三傳 目次に戻る |
| ■ 付録「幕末太陽族」たちのその後 長州藩志士焼討ち顛末 [地図七] 映画の核のひとつ、英国公使館焼き討ちが"実際に"行われたのは文久2年12月12日のこと。襲撃に参加したのは高杉晋作をはじめ、久坂玄瑞(映画では小林旭)、伊藤俊輔(博文−同、関弘美)、志道聞多(井上馨−二谷英明)ら13名。彼らは映画の通り土蔵相模に集結し、夜半まで酒宴を張ったあと八つ半(13日午前2時)ごろ、佐平次の手引きで若旦那・徳三郎たちと一緒に船で異人館に近づき...おっと、こりゃ創作だ。八つ半に公使館に忍び込み、自作の焼弾(爆弾)を使い全焼させた...これは事実。 このあとがちょいと洒落ていて、高杉や久坂らは芝浦の妓楼で燃え盛る公使館を肴に酒盛りを続けたそうだ。この公使館建設には複雑な政治的事情以外にも、風光明媚な御殿山の土地を奪われた庶民の反感も強く、映画の通り江戸市民の間でもこの事件を歓迎する雰囲気があったらしい。 この焼き討ちに関しての記録を読むと...これが実に笑えるのだ。真偽の程は定かではないのだが、聞多が土蔵相模の遊女お里の部屋に肝心の焼弾を忘れてしまったとか(結局使われなかった?)、一党がいざ公使館に近づいてみると周囲に大きな丸太の柵が連ねられており、誰一人こんなものがあるとは想像しなかったとか(この場面など映画の続きとして目に浮かぶようだ。「うーん、しもうたわい」とかね)。それに対して「こんな時の為に、ほれ、先程ノコギリを買(こ)うておいたのじゃ」と伊藤が差し出し、一同の尊敬を受けるという話が"伊藤の自叙伝にのみ"登場する(笑)。 放火のあともおかしい。現場を去ろうとした聞多は柵を乗り越えた際、勢い余って乾濠に落ちている(これは事実)。映画の二谷英明もかなりのお調子者に描かれていたが、どうも本当にああいうキャラクターだった様だ。泥だらけのまま引手茶屋に行き、聞多は土蔵相模に戻っている。翌朝、お里が焼玉を見つけて聞多慌てる、という逸話もあるらしいが、さすがにここまでくると、どこまでが本当かは判らないそうだ。 なお映画に大和弥八郎(武藤章生)が三田の辻番所に立小便をして捕まり(まったく今も昔もなんで同じことをやるんだろうねぇ)、持っていた焼弾を「見つかっちゃァ大変じゃから、ちいとづつ喰べた」という場面が登場するが、なんとこの逸話は本当らしい。 しかし、面白いなぁ。記録を追ううちに、どこか抜けていた長州藩の志士たちが、本当に幕末の太陽族だったと思えて来た。 ちなみに久坂はその2年後の元治元年(1864年)「禁門の変」で戦死、高杉もさらに3年後の慶応3年(1867年)、倒幕の志半ばにして病死、確か梅毒だったんじゃないかぁ?激動の幕末を生き抜いた伊藤は初代内閣総理大臣と千円札に、井上は外相、蔵相などを歴任した。井上が死んだのは1915年、大正4年のことである。 若旦那・徳三郎が女中おひさと共に千住の伯父さんの処で「魂を入れ替えて」仕合わせになれたかどうかは残念ながら不明、佐平次のその後の病状と、ヘボン先生に就いて亜米利加国に渡れたかどうかは更に不明である。 |