| Back to the menu |
 |
98/07/05 若人のための 日本映画入門 戦後黄金期編 |
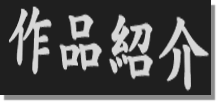
巨匠・黒澤明の世界
| 出 演 |
音 楽 |
撮 影 |
脚 本 |
監 督 |
野 良 犬 | ||||
| 千 秋 実 東 野 英 治 郎 他 |
山 本 禮 三 郎 千 石 規 子 木 村 功 |
三 船 敏 郎 志 村 喬 淡 路 恵 子 |
早 坂 文 雄 |
中 井 朝 一 |
黒 澤 明 菊 島 隆 三 |
黒 澤 明 |
|||
| 昭 和 二 十 四 年 新 東 宝 |
| クライム・サスペンスの元祖 |
| すべてがこの1本から始まった |
| 画面一杯に大写しになる犬の顔。舌を出しハアハアと息をしている。イタリア映画の様なオープニングだ。古式ゆかしい「冒険活劇」を期待した当時の観客はこの斬新なオープニングにさぞかし驚いたことだろう。いや、当時の観客だけではない。平成の時代に観た私だってかなり驚いた(ヴィデオではなく映画館のスクリーンで観たので驚きも一層であった)。そしてその顔に重なるナレーション「その日は、恐ろしく暑かった」...。 昭和24年の作品『野良犬』は日本初のドキュメンタリー・タッチの刑事物映画である。今ではあたり前となっているリアルな犯罪物、クライム・サスペンスを最初にやったのが黒澤のこの作品であった。 もちろん海外では数々の名作が撮られていた。しかし、なぜか日本ではチャンバラ映画の現代版、「活劇」の域を出ない作風ばかりだったそうだ。そこに、このリアリズム。当時の黒澤がいかに斬新な監督であったが察せられる。 戦後間もなくのことである。射撃演習から帰る若い刑事・村上(三船敏郎)がバスに乗った。満員の車内で身を寄せて来たのは、見るからにうさん臭そうな女・お銀(岸輝子)であった。女が降りる、ふと気がつくと持っていた筈の拳銃・コルトがない!共犯らしき男を追うが、炎天下の街でやがて見失う。村上は愕然とする。残りの弾丸は七発であった。 スリ係の刑事の協力で、お銀と接触した村上は、ピストル斡旋組織があることを突き止める。しかしそこに近づくためには、只、街を歩くしかないというのだ。敗戦の東京を、ぼろぼろの復員服を着て野良犬のように歩く村上。そして遂にそれらしい白ターバンの女(千石規子)に出会う。 しかし同時に淀橋で村上のコルトを使った強盗事件も発生する。奪われたのは大事な結婚資金であったという。村上は責任を感じ、辞意を示すが、上司は逆に担当を命ずる。そして相棒が登場。知性派の名刑事・佐藤(志村喬)である。 白ターバンの女の自白により、ピストル屋・本多(山本禮三郎)の存在が明らかになる。元締め的な位置にいるこの男、大の野球ファンだというのだ。刑事達が超満員の後楽園球場に張り込む。そしてある方法で本多を捕らえる。 本多の供述から、村上のコルトの行方が判った。遊佐(木村功)という復員兵が持っているという。今度は遊佐を探す二人。しかしそこで第二の犯行が起こる。今度の被害者は若妻だった。出張から帰り、妻の亡骸を見つけた夫が泣き叫ぶ。一刻も早く、遊佐を見つけなければ。 遊佐の手がかりとなるのは幼なじみのダンサー・ハルミ(淡路恵子)だけである。母と暮らすハルミの家に、村上が通う。ハルミはなかなか口を開かない。一方、佐藤は残されたマッチなどから、神田の簡易旅館にいる遊佐を突き止めた。電話で応援を頼む佐藤。いよいよ逮捕かと思ったその時、受話器の向こうから銃声が聴こえた。佐藤が遊佐に撃たれたのだ。村上の、コルトで。 遂にハルミが協力する、「朝6時に大泉駅に遊佐が来る」と。駆けつける村上。しかし、遊佐の顔が判らない!そして...。 拳銃を盗られた刑事、というネガティヴな設定にまず引き込まれる。そしてそれによって、勧善懲悪のチャンバラ刑事ドラマではなく、深い人間ドラマが繰り広げられる。確か、村上は全編を通じて一度も拳銃を発射しないのではなかったかな...。今から50年前にこの発想、黒澤の先見性たるや見事である。 |
 |
三船敏郎、志村喬 |
| そう、50年前の物語なのだ。スクリーンに登場する無国籍なスラム、村上刑事が野良犬の如く歩き回る雑多な街が、今我々が住む東京の50年前なのだ。あまりの変化にこれにはちょっと驚かされる。特にラスト、どこの山奥かと見紛う駅が、練馬区の大泉であるというのは本当に驚いた。武蔵野あたりとなっている佐藤刑事の家も一面の畑の中である。 しかし、だからこそ、面白い。同じ国とは思えないほど古い東京を舞台に、本当にスリリングな、全く古くないクライム・サスペンスが繰り広げられる。黒澤の往年の名作は、こうした古さと新しさの組み合わせで我々を魅了するのだ。 |
| かなりの作品を1ページ目で紹介したが、見逃せないのは『羅生門』(昭和25年・大映)、『生きる』(昭和27年・東宝)、『椿三十郎』(昭和27年・東宝)、『赤ひげ』(昭和40年・東宝)あたりか。 『羅生門』(昭和25年・大映) − 芥川龍之介の「藪の中」を原作としたシュールな時代劇である。昭和26年の第十二回ヴェネチア国際映画祭金獅子賞(グランプリ)受賞作品。「世界のクロサワ」の第一歩となった作品である。詳しくはこちらを。 『生きる』(昭和27年・東宝) − これも有名な作品である。老いた市役所職員、渡辺勘治(志村喬)は勤続30年無欠席が取り柄の冴えない男である。そんな渡辺が始めての無断欠勤をする。自分が癌で、余命幾許もないということが判ったのだ。ショックで動揺する渡辺。自らの禁を破り風俗に興ずるも、残るのは孤独感だけだった。 そんなある日、かつての部下・小田切とよ(小田切みき)が小さな工場で活き活きと働いているさまを見る。そしてせめてこの人生の最後に、なにかを残そうと決意する。 山のような未決書類の中から、たらい回しにされていた「水たまりを公園にして欲しい」という陳情書に目を留める。渡辺は僅かばかりの余命を、この公園造成に懸ける。役所の体質や、ヤクザの脅迫など小さな公園とはいえ次々に困難が降りかかる。 それらの障害を乗り越えて、遂に公園は出来上がる。そして開園式の行われた晩、渡辺は自らの作った公園で、ブランコに揺られ、「命短し、恋せよ、乙女」と歌いながら、息を引き取った。静かに粉雪が降っていた...。 有名な作品だし、こうしてあらすじを書くと超名画のように思えるのだが、イマイチ、展開にモタつきもある。一本目としてはお薦めしない。まずは大きく紹介した作品を観て、その次に是非。 『椿三十郎』(昭和27年・東宝) − 『用心棒』と並ぶ活劇の傑作。そもそも『用心棒』があまりにもヒットしたため、「三十郎でもう一本」と東宝側から頼まれて作られた映画である。同じ様な作品が重複するので、大きくは紹介しなかったが、こちらも傑作。『用心棒』を観たら次はこれであろう。とぼけまくりの小林桂樹、最後の最後に光る伊藤雄之助など脇役もイイ。アクション・シーンのパワーアップが目覚ましく、ラストには驚嘆するはずだ。 『赤ひげ』(昭和40年・東宝) − 三時間に及ぶ大時代劇。しかし活劇ではなく、江戸時代の「医療ドラマ」である。蘭学を学んだ医師の卵・保本登(加山雄三)が小石川療養所に着任する。保本は所長の新出去定(三船敏郎)に憤慨する。破天荒な性格と、蘭学経験がないことに不満なのだ。しかし、日が経つにつれて、この赤いひげを蓄えた所長・新出の行いに惹かれて行くのだった。知らないと思っていた最先端の蘭学知識までも兼ね備えている、新出のただならぬ才覚に驚きながら...。ヴェネチア映画祭主演男優賞に輝いた三船の熱演が見ものである。長いが、必見。 ここであえてお薦めしたいのが、次の二作品である。万人向けの面白さではないが、ヨーロッパ的な様な、実は極めて日本的な様な、そんな仕上がりになっている。ミニシアター派にはぴったりかもしれない...。 『どですかでん』(昭和45年・四騎の会) − 黒澤初のカラー作品であると共に、異色作でもある。母(菅井きん)は、揚げ物屋をしながら、特徴的な顔をした息子(頭師佳孝)を育てている。壁一面に息子の書いた電車の絵が張ってある。乗務予定を母に告げる息子、都電の運転手なのかと思いきや、彼は目に見えないレバーを鞄に仕舞い込む。彼の車両は彼にしか見えない。「どですかでん」と言いながら、街中を疾走する息子。 女房を交換する土方の義兄弟。近代建築のマイホームを夢見るルンペン親子。親戚に辱めを受ける哀れな少女など、その周りに住む、貧しい人々の描写が続く。映像はフェリーニ、ストーリーはデ・シーカとはちょっと強引か(笑)。 『生きものの記録』(昭和30年・東宝) − これも面白い。原爆の恐怖に苛まれて、精神のバランスを崩した工場経営者・中島喜一(三船敏郎)の物語。身内の財産争いなども絡み、喜一は工場に自ら火を放つ。精神病院に入れられた喜一、地球を離れて安全な星にいると思い込んでいる。窓の外の真っ赤な太陽を観ながら叫ぶ。「燃えとる燃えとる、とうとう地球が燃えてしまった」。 三船が「老け役」に挑戦した意欲作。『惑星ソラリス』(昭和47年・ソビエト・監督アンドレイ・タルコフスキー)のような、『アルファヴィル』(昭和40年・仏・監督ジャン=リュック・ゴダール)のような不思議な作品である。 |
| ここまでにしよう。「黒澤入門」としては十分な筈だ。名前だけは知っていた、という人が大半だろう。「世界のクロサワ」「天皇」といった言葉、そして近年の公開作から保守的な作家だと思っている人も多いかもしれない。それは、違う!ウォン・カーウァイの『楽園の瑕』('94・香港)と、タランティーノの『レザボア・ドッグス』('93・米)と同じパッションがあるのだ! 何でもいい、せめて一本、観て欲しい。黒澤を観るのは容易である。どんなレンタル・ヴィデオ店でも必ず数作はあるのではないか。場所によっては殆ど揃っているところもある。文字通り今まで「素通り」していたかもしれない、黒澤の棚に近づいて欲しいと思う。 しかし本当に体験して欲しいのは名画座での特集上映である。老若男女、本当にさまざまな観客で多分、満員になるはずだ。そして多分、観客の熱気に驚くはずだ。『用心棒』で書いた通り、それこそが日本映画全盛期の空気なのだ。暗闇の中、三船敏郎や志村喬とのタイムスリップも面白い。 今からでも十分、遅くはない。 |

さて次は名匠・小津安二郎の世界をご案内
上のテロップをクリックして下さい