| Back to the menu |
 |
98/07/05 若人のための 日本映画入門 戦後黄金期編 |
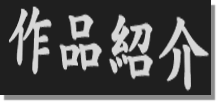
巨匠・黒澤明の世界
| 出 演 |
音 楽 |
撮 影 |
脚 本 |
監 督 |
七 人 の 侍 | ||||
| 稲 葉 義 男 津 島 恵 子 島 崎 雪 子 他 |
千 秋 実 加 東 大 介 木 村 功 |
志 村 喬 三 船 敏 郎 宮 口 精 二 |
早 坂 文 雄 |
中 井 朝 一 |
黒 澤 明 橋 本 忍 小 国 英 雄 |
黒 澤 明 |
|||
| 昭 和 二 十 九 年 東 宝 |
| 黒澤明の最高傑作 |
| 三船敏郎の天才にも気付くべし |
| 「シェークスピアの作品さえあれば演劇とはどんなものか分かるし、ドストエフスキーの作品さえあれば小説とはどんなものか分かる。それと同じように『七人の侍』さえあれば映画とはどんなものか分かる」−作家、井上ひさし氏の言葉である。 黒澤に気づくのは早かった。中学1年だったと思う。親に連れられて地元・テアトル鎌倉で観た『天国と地獄』で、完全にブッ飛んだ。黒澤とは何者なんだ!と思った。 『七人の侍』という代表作があることはすぐにわかったが、実は何年も観ずに放っておいた。若かったこともあり、「時代劇じゃなぁ...」と敬遠していたのだ。そして、社会人になってから観た。私は人生を悔やんだ。こんなに面白い映画が世の中にあったのか!と。 時代劇の枠も、邦画の枠も、関係ない。ジャンル無用。この映画のジャンルは「名画」である。これ以上の説明は不要だ。 名もない小さな村。回りは麦畑に囲まれている。季節は秋。麦穂はコウベを垂れ、平和な実りの風景に見えるが、残忍な野武士の襲撃を恐れ村人たちは恐怖に怯えている。とても自分達の手では守り切れない。長老が決断し、街から侍を連れて来ようということになった。利吉(土屋嘉男)ら村人が宿場街に出た。 しかし侍探しは難航、貧乏な村のために命を懸けてくれる者など簡単には見つからない。そんなある日、利吉らはひとりの老いた侍が僧侶に化けて盗賊を倒す場面に出くわす。その冷静な振る舞いに「このひとこそ」と考えて懇願、村の守りを委(ゆだ)ねる。 その侍、島田勘兵衛(志村喬)の最初の仕事は、更なる侍集めである。勘兵衛の英知に惹かれ、旧友・七郎次(加東大介)のほか、思慮深き五郎兵衛(稲葉義男)、どことなく滑稽な平八(千秋実)、若き勝四郎(木村功)、剣の達人・久蔵(宮口精二)が集まった。 村に向かう一行に対し、前に後ろにと付きまとう妙な男がいた。宿場街で暴れていた自称・侍の菊千代(三船敏郎)であった。木々の間を飛び回り、川魚を手づかみで捕らえる、野性児・菊千代も結局彼らに加わった。勘兵衛以下七名、「七人の侍」たちである。 一行が村に着いた。熱烈な歓迎...はなく、村人たちはただ戸板の隙間から疑わしげに伺うだけである。突然、野武士の来襲を伝える木片が打ち鳴らされた。一体どこにいたのかと思うほどの村人たちの群れ。あわてふためいて、七人の侍に助けを求める。しかし、これは、トリックだった。木片を叩いたのは菊千代であった。「なんだぁ、お前ら、出迎えもせずに。野武士が来たとなると『おさむらいさまぁ〜、おさむらいさまぁ〜』だと?!」。この時の三船の芝居、絶品である!私はここで「ああ、この人は天才だ」と思った。 そんな菊千代の機転もあって、侍と村人は次第に打ち解けて行く。訓練も始まった。あるものは剣を教え、あるものは心構えを説く。村人たちに語る平八、「我々が怖いのと同様、やつらだって怖い」。 いよいよ野武士がやって来た。まずこちらから忍び込み、野武士の砦に夜襲をかける。しかしそこには野武士にさらわれた利吉の女房(島崎雪子)がいた。女房はその姿を見られたことを恥じ、燃え上がる砦に身を投じる。そしてここで平八が撃ち殺された。敵は種子島(鉄砲)を持っているのだ。「これから役に立つ男であったのに...」勘兵衛は悔やんだ。 野武士三十余騎が村に攻め寄せた。全力を投じての反撃である。村外れの水車小屋が火に包まれ、ここから菊千代が赤子を助け出す。その子を抱きながら泣き叫ぶ菊千代。「この子供は俺だ!」。彼は野武士によって滅ぼされた農民の伜であったのだ。 このあたりの人間模様が実に面白い。最年少の勝四郎は、ストイックな久蔵に感服している。一晩がかりで敵陣に乗り込み、敵の種子島を奪って来た久蔵。誇るでもなく、奢りもせずに無造作に鉄砲を投げ出す。そんな久蔵を呆然と見つめる勝四郎、「あなたは立派な人だ。あなたは素晴らしい人だ」。久蔵は無言で眠るだけであった。 村の地形を活かし、袋のネズミにして敵を倒す勘兵衛たち。しかしこの戦いで五郎兵衛が命を落とした。 戦いは数日に及んだ。決戦の日は雨であった。敵は残すところ十数騎、五人に減った侍たちと村人が必死に応戦する。達人・久蔵も敵の弾に倒れる。銃声と共に崩れかかる久蔵が、最後の力を振り絞り敵を射抜く様、その強靱さは圧巻であった。 女子供たちが隠れる小屋に、敵の幾人かが近寄る。気付いた菊千代が後を追い、立ち向かう。どうなる菊千代。そして勘兵衛、勝四郎、七郎次は?。 世界中で観られ、愛されている名画である。面白いエピソードがある。国によって「人気のある侍が違う」というのだ。アメリカ人は名将・勘兵衛が好き、フランス人には寡黙な才人・久蔵が人気。天衣無縫の野性児・菊千代が好きなのは...ご想像通り、イタリア人である。 |
 |
往年の上映ポスター 中央上が’菊千代’さま |
| そもそもこの「菊千代」という名前からして可笑しい。名もない農民の伜を恥じて、どこからか盗んだ系図を元に、勝手に「これが俺だ」などといっているのだ。算術など出来ない菊千代、うっかり子供の名前を指さしてしまい、「菊千代さま、とても子供には見えないが」などとからかわれる。良く出来た活劇は喜劇までも摂り込むということか。 そして実は最初は想定されていなかったキャラクターなのだそうだ。当初は「六人の侍」だったのだが、脚本の小国英雄が途中で発案したらしい。しかしこの役こそ、三船敏郎の真骨頂、疑う村人たちに「わんわん」と吠えてみたり、後ろ足で砂をかけてみたり、天才的とも言うべき「暴れ方」で我々の視線を釘付けにする。ところがそうした演出の多くが三船のアドリブで、三船曰く「地で行った」というのだから驚く。これが地?一体何者なのだ?。 上映時間3時間27分。しかし、あっと言う間だと思う。三船を、志村を、そして黒澤を知るのために、これ以上のフィルムは存在しない。 |
| 出 演 |
音 楽 |
撮 影 |
脚 本 |
監 督 |
用 心 棒 | ||||
| 土 屋 嘉 男 司 葉 子 他 |
河 津 清 三 郎 山 田 五 十 鈴 加 東 大 介 |
三 船 敏 郎 東 野 英 治 郎 仲 代 達 也 |
佐 藤 勝 |
宮 川 一 夫 |
黒 澤 明 菊 島 隆 三 |
黒 澤 明 |
|||
| 昭 和 三 十 六 年 東 宝 |
| 日本一の娯楽映画 |
| もしかしたら『七人の侍』よりも面白い?! |
| そしてこの映画は「ジャズ」である |
| 面白い。たまらない。面白すぎて涙が出た。黒澤自ら「徹底的に娯楽を追求した」と語る『用心棒』(昭和36年・東宝)、もしかしたら、『七人の侍』よりも面白いかもしれない...。 この映画はジャズである、とも思う。主人公の三十郎(三船)は天才的なソロ・プレーヤーであり、サイドを固める権爺(東野英治郎)、卯之助(仲代達也)のプレイも絶品、雇われの荒くれ者集団はビッグバンドを思わせる。観ているうちにじわじわと浮かんで来たのが、ジョニー・グリフィン・オーケストラの名盤『ビッグ・ソウル・バンド』('60)だ。全体を流れる痺れんばかりのビート感。この二作品には同じ血が流れていると思う。ジャズ用語でいう「オフ・ビート感覚」である。 イメージだけではない。実際、佐藤勝のサウンド・トラックもどことなくジャズ風である。佐藤のスコアも「徹底的に遊ばせてもらった」という感じだった。 宿場街である。ぶらりとやって来た男(三船敏郎)は街の雰囲気がおかしいのに気付く。戸は閉ざされて、往来は絶えている。二人の親分が縄張り争いを繰り広げているのだ。 用心棒を掻き集めていた清兵衛(河津清三郎)に、男は売り込みをする。相手方、丑寅の若衆(ジェリー藤尾ら)数人をあっと言う間に叩き切り実力を見せつけた男は、桑畑を眺めながら名を名乗る。「名は...桑畑三十郎。もっともそろそろ四十郎だがな」。 落ち着いたかに見えた三十郎だったが、清兵衛の妻・おりん(山田五十鈴)が「金を半分だけ渡しておいて、あとで殺してお仕舞い」などと恐ろしいことを言うのを聞き、ここを逃げ出す。そして居酒屋・権爺(東野英治郎)の処に居座る。暫く様子を観て、高く買われる方に付こうというのだ。 今度は丑寅(山花茶究)の方に付いた三十郎。ここで丑寅が囲っていた百姓の娘・ぬい(司葉子)を逃がし、清兵衛方の仕業だと誤魔化す。その際、村はずれの小屋をひとりでぶち壊し「こりゃ15人くらいの仕業だな」としらばくれる。映画館の館内はここでドっと沸く。しかしこの振る舞いは丑寅の弟、ピストル遣いのキレ者・卯之助(仲代達矢)に見破られ、半殺しの上、見張り付きで蔵に放り込まれてしまう。 三十郎がなんとかここを逃げ出して、念仏堂で静養しているうちに、丑寅方が清兵衛一家に殴り込みを掛けた。しかも居酒屋の権爺も、三十郎を逃がしたために卯之助に掴まってしまったのだ。 知らせを受けた三十郎は「許せねぇ!」と街に向かう。腰の刀は丑寅に奪われて、懐にたまたま持っていた出刃包丁しかない。「それでどうやって戦うんだい」と聞く棺桶屋(渡辺篤)に一言、「刺身にしてやる!」。ここで再び爆笑である。 いよいよ三十郎と丑寅方・卯之助の対決。ピストルを持った卯之助に、三十郎は勝てるのか?三十郎そして権爺の運命やいかに! 究極の娯楽映画である。観る者を楽しませようとする仕掛けが山ほどある。まず、三船三十郎のとぼけた感じが最高である。権爺とのやりとりにも必ず笑いが仕掛けられている。仲代卯之助には「ここまでやっていいのか」という意見もあったそうだ。ピストルはともかく、この卯之助、首にタータン・チェックのスカーフを巻いているのだ。黒澤はそんな外野の意見に「横浜あたりにいたんだよ。不思議はない」と言い切った。 |
 |
三船の三十郎 左は沢村いき雄 |
| 音楽面でもそんなところがある。三十郎をもてなそうと、おりんが連れて来た女郎たちが、踊りながら、ラテンのリズムで拍子木を叩く(笑)。これは絶対に有り得ない話だ。江戸時代の日本にモントゥーノもクラーベもあるわけはない。しかし、これでいいのだ。これは娯楽映画なのだ。 出来ることならばヴィデオではなく名画座の上映を観て欲しい。館内はむせ返るばかりの熱気と、笑いに包まれるはずだ。そしてそれこそが「日本映画全盛期」の空気なのかもしれない。 |
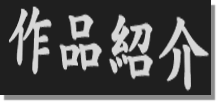
続いて現代物の名作をご紹介
上のテロップをクリックして下さい